なんちゃって有馬富士縦走
スポンサード リンク
平成21年5月2日(土) メンバー おひとりさま
JR新三田駅〜有馬富士公園〜有馬富士〜千丈寺湖〜JR広野駅
三田市のシンボル、有馬富士(標高374m)は果たして登山の対象となりえるのだろうか。
どの方向から見ても富士山に似ている独立峰の有馬富士は、西国三十三箇所巡礼を広めたことでも知られる花山法皇(968〜1008)が、北麓の西国三十三箇所番外「東光山花山院菩提寺」で『有馬富士 麓の海は 霧に似て 波かと聞けば 小野の松風』と詠まれたように、千年以上も続く由緒ある名を持つ山だ。
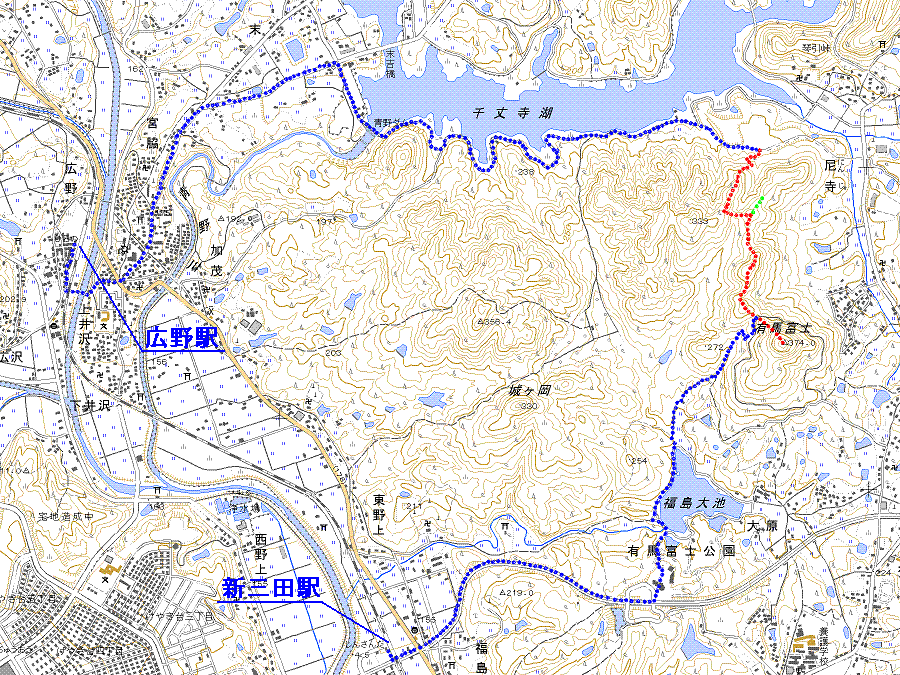 | |
今回の有馬富士縦走コースは起点をJR新三田駅とし、有馬富士公園・福島大池から有馬富士頂上を目指して登る。
下山は北へ、皇太子殿下が臨場された平成17年全国育樹祭の開催と共に開かれたハイキングコースで千丈寺湖へと下る。氷ノ山の殿下コースのように皇太子殿下が歩かれたわけではないが、ある意味「殿下コース」の一つに違いない。
下山後は千丈寺湖畔の舗装道路を延々と歩き、青野ダムで昼食休憩。そしてさらにJR広野駅への車道歩きが待っている。山歩きというよりも、山行概念図のように青線ばかりの車道歩きの一日だった。
車道歩きの前に
私の住む姫路市から有馬富士は遠く、JRで行くと往復の交通費は3,780円で、費用対効果は10円/mとなる。本物の富士山が、大阪からの登山バスツアーなら5円/m程なのに比べたら高すぎる。
ところが、神姫バスにより三ノ宮から三田行きの特急路線バス(特急38系統)が運行されているのを見つけてしまった。神姫バスなら土日祝日にエコ定期券制度が使えて、JR三ノ宮への定期券も持っているので、有馬富士は200円(0.5円/m)で登ることができる。
7:40
JR三ノ宮駅東側高架下の神姫バス三ノ宮バスターミナルから、特急38系統のうち「エルム・学園7丁目」行きに乗る。土曜日なのにスカートの短い女子高校生が多く、座席の半分以上が埋まっている。
 | |
乗車扱いのみの新神戸駅を過ぎると、車内運賃表示機に「弥生が丘5丁目 700円」と、いきなりローカルなバス停名と高額な運賃表示が出て驚く。三田までは、新神戸トンネル・阪神高速7号北神戸線・六甲北有料道路と高速道路・有料道路ばかりを通るが、別に特急料金をとられるわけでもない。
8:31
エルムプラザ前バス停で下車。車両は三田営業所所属の三菱自動車U-MS826PA、貸切車からの改造で車歴は16年(神姫博バス館より)、バス愛好者の間では特高車(特急高速車)と呼ばれている。
 | |
エルムプラザから新三田駅へは歩ける距離だが、歩いている途中で8時42分発の新三田駅行き神姫バスに追い越されるのは目に見えているし、そのバスも100円で乗れるので待つことにした。
8:49
普通の路線バスで新三田駅に到着。広々とした駅前広場には次々とバスがやってきて、三田市におけるバスの中心地のようだ。でもどうしたわけか、三ノ宮から新三田駅への神姫特急バス路線はない。
駅前広場の野外彫刻(新宮晋氏作の大地の詩)の写真を撮ったり、ハートインでお昼ご飯を買ったりする。
 | |
車道歩き
9:05
有馬富士公園へと、新三田駅の南端から線路の下をくぐる道への階段を下りる。
歩きやすいだけがとりえの広い車道脇の歩道よりも、福島大池から武庫川へと注ぐ大池川沿いの緑溢れる地道を歩いた方が数倍は楽しいだろうが、歩き始めていきなり迷子になるのは困る。有馬富士公園の拠点施設も覗いて見たいし、詰らないが車道歩きを選択する。
 | |
9:27
新三田駅から20分ほどで有馬富士公園正門に着いた。園内ではGWの何かイベントを行うのか、テントを建てて忙しそうに準備をしている。
 | |
9:44
あるもの(東山嘉事氏の「鳥虫戯石」)を探すも、園内は予想外に広く早々に諦め、ガーデン階段で福島大池へ下る。
普通こういう公園なら名前の中に「自然」が入り「有馬富士『自然』公園」となりそうな気がしていた。でも、目の前に広がる光景の中には『自然』などひとかけらもなく、全てが人の手により造られたものしかない。まあ、知恵を絞って人受けするように造られているので、好ましい風景であるのは間違いないが、都会の高層ビルの間を歩くのと大差ないと感じた。
 | |
9:48
福島大池に映る「逆さ富士」を写したかったのだが、「人が写ってこその写真」を標榜する野歩記では風景写真などありえなく、あくまでも主題は私の後姿にあり、これでいいのだ〜♪これでいいのだ〜♪。
 | |
9:54
園内案内図を熟読したと自分では思い込み、福島大池の「西側」の散策路を進む。東湖畔を行っていたら、東山嘉事先生の「鳥虫戯石」に出会えたかもしれないし、少しはまともな有馬富士縦走になっていたのにと、後々後悔することになる。
 | |
9:56
福島大池の北端で道は左右に別れる。左手へは「←有馬富士登山道 ●登山をする服装で山登りをして下さい ●足元に注意して登山して下さい」の案内板があり、この先に登山口があるものと信じてしまったが、実はここが登山口で、しかもすでに私の歩いているのは登山道であったことには後々気付くことになる。
 | |
10:03
ログハウス風の休憩所があり、広々とした道が続く。この道が有馬富士公園ではハイキングルート(メインルート)と呼ばれるもので、これ以上の整備は不可能な究極の登山道だ。
 | |
有馬富士公園 ハイキングルート
- ハイキングルートの大部分は自然地形を利用した山道です。急坂・流れ・岩場などがありますので、各自の体力に応じた歩行を心がけてください。
- 表示ルート以外の道は迷う可能性がありますので、みだりに立ち入らないで下さい。
- ルート周辺で土砂崩れや倒木などを発見された場合は、お知らせください。
パークセンター 電話079-562-3040 三田土木事務所 電話079-562-8875
まあ注文の多いハイキングコースだが、火気厳禁、ゴミを捨てるな、勝手にマーキングするな、などは暗黙の了解事項になっているのだろうか。でも些細なことだが、1.と3.の文末は「ください」なのに、2.だけは「下さい」になっていることに、どのような意思が込められているのかと深読みしてしまう私がいた。単なる誤記だと思うが、思わす携帯電話に手がのびるところだった。
10:05
新緑のあまりの美しさに、思わず微笑を辺りかまわず撒き散らしながら行く。春を待ちわびたように咲く可憐な花なんかよりも、私はこの新緑が一番好きだ。
 | |
10:08
道なりに右へ進むと、頂上南側の頂上広場・わんぱく砦から有馬富士頂上へと登れそうだが、「←山頂へ」の案内板は左に分かれる道を示している。どちらに進むべきか迷ったが、たくさんの車道が山頂を取り巻き錯綜しているこの有馬富士で、案内に逆らって迷子になっても困るし率直に案内に従い左の道に入る。
 | |
10:09
道は車の離合が難しいほどに狭くなったが、一般車の入れない舗装管理用道路なので、この幅があれば大型ダンプカーでも入れるだろう。でも、まさかもうすでに登山道を歩いているとは思いもよらず、登山口はどこにあるのかと、いつもとあまりに勝手の違う山なので少々不安になってきた。
 | |
10:14
途中、山頂方向へ「あじさいの小道」なる地道の遊歩道ぽいものが別れていた。土地勘もないしこのまま進んでもよさそうなので、そのま舗装管理道路を進んでしまった。
帰宅後に見た有馬富士公園公式HPの案内図で、「あじさいの小道」から「つばきの小道」を経由して「わんぱく砦」から有馬富士頂上に至ることが分かった。現地の各所に立つ案内図には、なぜか「小道」が記載さていないので、どこへ行くの分からない、はたまた周回路になっているかもしれない「あじさいの小道」に足を踏み入れることなどできない。
 | |
10:19
右手から合流して来た道がどこから来たのか分からないが、「←有馬富士山頂へ」の案内は私の進行方向を指している。ここまでにいくつもあった別れ道のうち、案内に逆らってどれか一つでも右に行ったらよかったのにと悔やまれるが、ここも案内のとおりに直進してしまった。
 | |
ようやく山道らしくなり、頂上へ
10:22
こんなはずではなかったのに、いつ間にか有馬富士頂上北側の千丈寺湖への分岐点まで来てしまった。
その分岐点手前に「山頂へ→」が階段道の入口に立っている。千丈寺湖へはここから下る計画なので、有馬富士頂上まではピストンとなり「有馬富士完全縦走」の野望は朝露の如くはかない夢と消えさってしまった。
 | |
10:26
舗装管理用道路だったのか、遊歩道だったのか、はたまた登山道であったのかもしれない舗装道路歩きから開放されたが、今度は私の脚の長さを嘲笑うかのように段差の大きな丸太階段道だ。踏み段の幅は十分にあるので段差をもっと小さくできただろうに、標高差を予算で割って段数を決めてしまったのだろう。
 | |
10:29
丸太階段道が終わると、今度は本格的な岩がちな急な登り。舗装管理道路・丸太階段道に惑わされて、サンダルやハイヒールで登ってきたら大変だ。
 | |
10:33
楽しみにしていた有馬富士登山は10分で終わってしまった。広々とした四等三角点標石(点名:有馬富士)のある有馬富士頂上は木立に囲まれ、かろうじて南側の展望が得られるぐらいで、眺めは悪い。
 | |
まさか有馬富士にはないだろうと思っていた登頂記念プレートだが、4枚も下がっているのを見つけた。吊るした皆さんは、自己顕示欲の権化たる私の足元にも及ばないレベルだが、ここに公開することで少しは満足されるのではなかろうか。私は「撮っていいのは写真だけ、残していいのは思い出だけ」を信奉し、登頂記念プレートはゴミにしか見えない。
- 374m 有馬富士 JL3VOG
- △374M 2003.9. 有馬富士
故郷を歩く会
西尾伸作 八田二郎 種田成樹 香月輝一 新田洋子
吉田静江 吉岡清治 西田優子 米田マル子 - ひぐらしの会 2009.3.21
- かすれて読み取れず(1枚)
下山、そして千丈寺湖へ
10:43
何をそんなに息を切らせているのか、必死の形相で登ってきた初老グループと入れ替わりに下山開始。私はいつも頂上近くの物陰で息を整えてから、何食わぬ顔で「ヘッ、こんな山たいしたことないな」と呟きつつ、頂上を踏むことにしている。
10:52
下山は10分も掛からなかった。
さて、ここから千丈寺湖へは、三つほどのなだらかなピークを越えて行くわけで、道標によると距離は1.8kmとある。
 | |
張り紙が案内板の半分近くを隠している。その下に何が書かれているのか気になるが、とりあえず張り紙を読んでみよう。
公園を利用される皆様へ (お願い)
いつも市立有馬富士公園をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度、市立有馬富士公園内を一時利用いたしまして、下記の期間イノシシなどの有害鳥獣を捕獲するための檻を設置することになりました。これは有馬富士公園が整備されて以来、有害鳥獣の捕獲が公園内に入っておらす、そのためイノシシなどの有害鳥獣などが園内に増殖し、周辺農家の農作物や田畑等を荒らし、年々その被害は拡大しております。
本市では、こういった農家の農作物被害を救済すべく、関係機関とも協議した結果、ます市立有馬富士公園から捕獲用檻を設置することで決定いたしました。
本来、公園とは市民の方が集い、憩う場所であり、場違いともいえる捕獲用檻を設置することは大変恐縮でございますが、、安全対策には万全の措置を取る所存ではありますので、何卒、ご理解の程、よろしくお願いします。
なお、檻の前には注意看板を設置させていただいておりますが、特にお子さんをお連れの方は、危険なので決して近づかないようにご注意くださるようお願いいたします。記
1. 設置期間 平成20年10月15日(水)〜平成21年5月31日(日)問い合わせ先
三田市経済環境部経済環境室農業振興課農林振興係り
TEL079-559-5090(直通)
何を言いたいのかが最後まで読まないと分からないが、そういえば舗装管理道路脇に捕獲用檻と注意看板があった。
分かりにくさの原因は、公園内に檻を置かせてもらう側の言葉だけがへりくだった冗長な文章にあり、こういうのは有馬富士公園当局によるビッシとした警告文にして欲しかった。
でも、振り向くとハチとマムシの注意喚起案内板があり、特にマムシが生々しすぎて夢の中にも出てきそうで、なんか小さいときに見たらトラウマになりそうだ。分かりにくいのも困るが、こんな一目で私を震え上がらせるのも困ったものだ。
 | |
10:55
舗装管理道路から北に別れて、普通に歩いたら30分もかからない千丈寺湖までの稜線歩きが、今日の山行のというかハイキングの核心部だ。ほんの緩やかな坂も丸太階段が整備され、小学生千人の団体同士がどこででもすれ違える幅広のハイキング道が、千丈寺湖と有馬富士を結んでいる。
しかし、有馬富士から千丈寺湖まで行って帰る、あるいは逆に千丈寺湖から有馬富士に登るハイカーなどいるわけがなく、このハイキングコースはオーバースペック過ぎて、自然破壊の見本にしか見えない。
有馬富士自体にもっと魅力があれば、こっちからも登ってみるかという気にもなるが、舗装管理道路が中腹を取巻いている山などにもう二度と登りたくない。でも矛盾しているが、麓に住んでいたら暇があったら登りたくなりそうな山ではある。
 | |
10:59
けなしてばかりでは、私の精神衛生上もよからぬ影響を与えそうで、ここからは褒めちぎろう。
稜線を行く道はよく手入れされていて見通しもよく、私の大好きな落葉雑木林の新緑が頭上から降り注ぎ、もう現世を離脱して天国か極楽を歩いている気分にさせる。こんな道なら一日中歩いても楽しく、真夜中に月明かりに照らされた中も歩いても面白いだろう。
 | |
11:02
二つ目のピークへの登りだろうか、丁寧な仕事の丸太階段を気持ちよく登らせてもらう。
いくら段差と脚の長さに乖離があろうと、階段道ほど登りやすく下りやすい道などこの世に存在しない。丸太階段は土砂の流失を防いで道が荒れることもなく、何千人何万人のハイカーが行き来しようと誰一人脚を滑らすこともない。誠に丸太階段道ほどハイキング道として適したものはない。かな。
 | |
11:05
稜線を行くハイキング道なので展望がよさそうに思うが、残念ながらはかばかしくない。冬場なら葉を落とした雑木林越しに外界が見えるかもしれないが、今はほんの少し東側が見えるだけだ。
 | |
11:09
二つ目のピークからの下り、うねうねと緩やかな階段道を下る。
コンデジなら当たりまえだが、最近のデジタル一眼レフカメラにも動画撮影機能が付き始めた。しかし私のものに付いていないが、創意工夫と熱意さえあれば叶わないことはない。下の擬似動画は、対応するカメラなら20m(キヤノン)〜50m(ニコン)離れても、赤外線リモコンでシャッターを切ることができるベルボンTWIN1 R3-UTを用いたものだ。
何十メートルも離れたら、標準レンズでは人物は小さくしか写らず利用価値があるかなと思うだろうが、このように目を引くものを撮ることができる。
 | |
11:15
この稜線の道に入った時に一人のハイカーに出会い、もうすぐ三番目のピークに付く前にトレイルランナーが追い越していった。出会ったのは結局その二人だけだった。道はよいし、雰囲気だけはどこの山にも負けないのに、少し寂しい、いや静かな山歩きが楽しめるからよしとしよう。
 | |
11:17
三番目のピークで道は別れている。直進は「千丈寺湖 1.6km」、稜線から西に離れる道は「千丈寺湖 1.2km」、やって来た道は「パークセンター 2.6km」と道標に表示されている。この道標だと100人中100人が千丈寺湖まで0.4kmも近い稜線を離れる道を選んでしまうだろう。事実、私がそうだった。
でも真っ直ぐ稜線を辿れば、花山法皇の御廟所もある西国三十三箇所番外「東光山花山院菩提寺」へ行くこともできたろうし、尼寺(にんじ)や琴引峠の由来も知ることができただろうにと残念でならない。でもでも、思い残すこことがなければ、再訪するきっかけがなくなり、これでよかったのかもしれない。
 | |
11:19
稜線から別れ西側へ下る道は、333m標高点の山塊(加茂山)との鞍部を目指し一直線に下る。
 | |
案内板には明確なルートが描かれていたが、山行をより楽しくするために適当にさっと見ただけだったので、てっきり鞍部から谷沿いに下るものと信じていた。だが鞍部から西側の尾根へ登り返すではないか。
このハイキング道の設計者は、暗い谷歩きの楽しさというものを知らず、これまでの人生は常に明るい明るい尾根ばかりを歩いてきたに違いない。辛く悲惨な思い出したくもないような暗い人生経験を積んで、明暗のある、変化のあるハイキング道を設計できるようになって欲しい。
11:25
千丈寺湖の青い湖面がちらちらと見えてきた。山と湖という絵になりそうな景色なのだが、周囲の雑木林が濃すぎて全開の眺望を得られる地点はなかった。
1ケ所ぐらい湖側の木々を全て伐採し展望所を造っても、「なんて事をするんだ」なんて悪態をつくのは私ぐらいで、全てのハイカーは「うわっ、きれい」と歓声を上げるに違いない。だらだらと眺望もない道をここまで歩いてきて、見えたのは木々ばかりでは、せっかくの素晴らしい風景がもったいない。
 | |
11:32
千丈寺湖畔レベルまで下りたが、千丈寺湖は見えない。周回路と思われる道の合流点の道標は「↓千丈寺湖0.6km ↑パークセンター3.6km パークセンター3.1km→」とわけわかめ。有馬富士へ登ろうとやって来たハイカーが、この道標の前で戸惑っているのが目に浮かぶ。
こんな劣悪な道標がどのような経過で計画され、そして何のチェックも入らずに、誰も何も不審に思わずに作成設置してしまうという、そら恐ろしい組織がこの有馬富士公園を運営していると思うと、そのシンボルとしての有馬富士が可哀想になってきた。
 | |
青野ダムへの車道歩き
11:38
皇太子殿下御臨場のもと平成17年10月30日に行われた第29回全国育樹祭の跡地は、何もない広いだけの芝生の広場だ。周囲の風景から隔絶した、申し訳程度に周辺に木がちょぼちょぼと植えられているだけの、無残な風景が広がっている。この有馬富士公園が目指しているのは自然との調和などではなく、自然の征服としか思えない。
 | |
11:46
大芝生広場の、展望所で行き止まり遊歩道から抜け出して、周回道路を見つけ出し、ようやく千丈寺湖畔へと下りることができた。加茂山第3公園では、まだ水遊びの時期には早いのか、バス釣りのボートが一艘だけ浮かび、ボート降着場から数人が竿を延べているだけで静かな湖畔だ。
 | |
11:53
火気が使用可能な加茂山第2公園からバーエキューの香りが漂い、私のお腹の虫も鳴き始めた。ここでお昼ご飯にしようかなと一瞬思ったが、みじめになりそうで止めた。よい判断だったと思う。
 | |
12:03
千丈寺湖畔には周回散策路があるものと思っていたが、あるのは点々と存在する小公園の中だけだ。そこに入るとバーベキューをしている家族に胡散臭い顔をされるのがおちで、私は車道を歩くしかない。おまけに大部分の車道と千丈寺湖の間には木々が茂り、湖面はほとんど見えない。なんか踏んだり蹴ったりで、腹が立ってきた。
 | |
12:10
入り組んだ千丈寺湖の脇を行く道路も、同じく入り組んでいる。地図を見るとたいした距離ではないが、実際に歩いて見ると行けども行けども当面の目的地、青野ダムに辿りつかない。
今時分はツツジの季節は終わりかけフジの季節になっているが、高い木から下がるばかりで写真を撮っても面白くない。ただ一箇所だけ道端に咲いているフジがあり、写真をパチリ。
 | |
12:18
下山してから1時間近く湖岸を歩き、青野ダム(高さ29m、長さ286m、竣工昭和62年)に着いた。六甲山中には青野ダムよりも巨大な砂防ダムがいくらでもあり、上流側から見るとなんてこともない詰まらなそうなダムだが、下流側を見ると結構迫力がある。なお道路はダムの上を通っている。
 | |
12:25
ダムの右岸側はダムサイト公園で、新宮晋氏による野外彫刻作品が2点(水の木・星の立像)、環境造形Qによるものが1点(千丈寺湖 サンクレセント ドルメン)あり、ここまで延々と歩いた疲れが一挙に癒された。
 | |
12:47
お昼ごはんは新三田駅ハートインで買ってきた「ミニ俵べんとう1 税込320円」。全体が手のひらに乗りそうな可愛らしさで、正に私のために作られたものだ。食べた後は、少しお昼ね。
 | |
13:39
ダムサイト公園の近くにバス停があり、三田駅行きのバス路線が通っているのだが、本数は1日3本で次は1時間後の14:44。こうなったらJR福知山線最寄駅の広野駅まで歩くしかない。なんか今日は山登りというよりは車道歩きの一日になってしまったな。
14:05
30分弱で広野駅に着いた。次の列車の時刻を調べてから駅前の、これも予定のうちの「武庫川橋りょう」モニュメントを四方八方、クローズアップと30枚ほど撮りまくる。このモニュメント、ただの鉄橋の切れ端を置いているだけではなく、上に蒸気機関車と電車のオブジェが付いているので、立派な野外彫刻となっている。
 | |
鉄橋「武庫川」
日本で始めて鉄道が、開通したのは明治5年、神戸と大阪間が結ばれたのは1年後の明治7年、5年後の明治10年には、京都〜神戸間が開通しました。
当時、三田では、阪神間への物流の手段として、武庫川に水路を開いて川船を走らせたものの、あえなく頓挫したときでした。
明治32年には、計画から開通まで、紆余曲折を乗り越えて阪鶴鉄道が開通し、舞鶴〜大阪間を乗り換えなしで結び、人や物の流れに大きく貢献しました。
その後、めいじ39ねんには、「日本国有鉄道法」の施行により、国に買収され、明治40年には、国有鉄道の「福知山線」となり、阪鶴鉄道の幕は閉じました。
この間、華々しく見送りを受けて戦地に向かった人。……終戦で幸いにも生きて故郷に帰還した人。……食糧難時代の車内の湯槽風景。……等時代に移る風景は、時と共に変化しました。
現在は、通勤する人。………旅にでる人。………この地へくる人。……等々、広野駅、鉄橋武庫川は、そんな多くの人々の姿を見つめてきました。平成9年3月吉日 広野商店会寄贈
武庫川橋梁 設 計 福知山鉄道管理局 施 工 大鉄工業株式会社 設計荷重 KS-18 基 礎 工 岩盤 基礎根入 天端より8.20m 着 手 昭和29年11月1日 竣 工 昭和30年3月30日
大阪駅行きの丹波路快速に乗ると、もう三田駅、いや今の時間なら神鉄フラワータウン駅で、三ノ宮駅行きの特急100円バスに乗り替える気力はうせて、気が付けばそこは大阪駅だった。
スポンサード リンク