�b�R�s�L�^�ɂ��ǂ� �b�z�[���ɂ��ǂ� �b
��j��A�����R�i�P�H�s172.9m�j��
�o�R���͂�������̂��낤
�X�|���T�[�h �����N
����20�N5��3���i�y�j�@�@�����o�[�@������
���V�݉Ɠo�R���`����`�c���R�蒬�o�R���`����`�҈�o�R��
 | |
�o�R�����A����_�L���́A�S�Ď������ݒn�m��̂��߉��ɕt�������O�ł��B
�����őS�o�R�����𖾂��邼
4��20���́u����A�����R�i�P�H�s172.9m�j�ɓo�R���͂�������̂��낤�v�̑����ł��B�����͔����R�̓o�R���E�o�R���̐����������𖾂��ׂ��A�܂��͒��ォ��k�������̒����^���N�i���ہj�ƐΒi�̂���k��������ڎw�����Ǝv���B
10�F01
���V�݉Ɠo�R������ʐ^���B��Ȃ���A20���قǂ����Ĕ����R����ɓ����B
�O�p�_�W�߂��̖ɓ����N���A�z���_�[���݂邳��Ă��āA�O��͋������A�����͔����R�Ɠ��ׂ�88m�W���_�ƙ�̂��鏬�R�̓o�R���}�b�v�������Ă����B���Ƃ������A�T���J�n�O�ɖړI��B�����Ă��܂��������肽���A���߉�ȁA����܂��Ƃɐe�Ȑl��������B
�k���������r�ցi�����ƊE�ł͊W�̂���^���N�ł��r�ƌĂԁj
10�F16
�C����蒼���A�L�A�Q�n��N���A�Q�n���������钸�����ɂ��āA����_F��ڎw���k�����̔����֓���B���̉��R����t�ɂ͈ē����������Ă�����̂����邪�A���̎�t�ɂ͂Ȃ������B
 | |
10�F18
�O����ʂ�������_F�ɒ������B��������E�͖k�������A���͖k�������ւƕ��Ă���i�����̖��O���������ɕt�������́j�B
���������V���[�g�J�b�g����G�EH�Ԃ��܂������ĂȂ��̂ʼnE�ɐi�ށB�����ɂ́u���c���R�蒬�o�R���ցE�����ǃ^���N��/�k�V�݉ƁE�V�݉Ɠ��E�c�����꒚�ړo�R���ց��v�Ƃ����A����̈ē����������Ă���B
�ł��A����ɂ��������[�g�}�b�v�����Ă��܂��A���̂Ȃ��肪�������Ă��܂������́A�ʔ��������ǂ��납�A���l���|���܊����̃|�C���g50���t���ł��܂���5�N�ԕۏ��t���Ă��܂����C�����B
����ǂ������R�ɓo�������Ƃ��Ȃ��̂ɁA���̋L�^��ǂ�ł��܂����M���̎����v���ƂȂ��������ɂށB�ł��A���̎R�͕P�H�s������̃��[�J���ȎR�Ȃ̂ŁA�����̃n�C�J�[���K��邱�ƂȂǍl����ꂸ�A��𑱂���B
 | |
10�F22
����_G�ŁA��������k�������ւ̒Z���H�֓���B��������̒Z���H�Ƃ������A���H�́A���d���������������ł��y���o����悤�ɂƁA����b�̊��d�͂���J�������̂�������Ȃ��B
 | |
10�F24
�Z���Z���H�͂قڐ��������B�Ďu�Ƃ������Ɛ�J�����f�p���͑S���Ȃ��A�@�B�͂�p���Ĉ�C�ɊJ�킵���l�q������������B�����Ă��铹���������R�ɂ܂������łȂ��A����ĕt�����悤�ȁA���̓�����͕��������݂Ɋ������B
 | |
10�F27
�Z���Z���H�͒����I���A�k��������̕���_K�ɒ������B�[�����Ɂu���c���R�蒬�o�R���ց@�������ǃ^���N�ցv�̈ē����������Ă���B
 | |
10�F30
�k�������͐^�������Ɋɂ₩�Ȃ̂ŁA���������ɐ^�������ɕt�����Ă���B
 | |
10�F41
�k�������ɂ����d���S����2�{�������Ă��āA�݂��ɋ߂��ɂ���A���㑤�́u�a�����@�O�v�Ř[���́u�P�H�x���@�O�j�v�ŁA���ꂼ��k�������ɗ����̂�����ԂÂႢ�ԍ����U���Ă���B��ʂɑ��d���S���̔ԍ��͎Ⴂ�قǓd�����ɂȂ�̂ŁA�����̑��d���͐�����k���ւƓd�C�𑗂��Ă���͂����B
 | |
10�F43
�[���̓S������́A���ʂɔ��R�i�U���R�j�������ĂȂ��Ȃ��̓W�]�n���B
���̔���������n�߂����납��A���h�Ԃ̃T�C�����̉������ӂ��玟�X�W�܂��Ă���悤�ɕ������Ă������A�ǂ������Ύ��Ȃ̂��낤���B���̕����ɉ����オ���Ă���̂͌����Ȃ��B
 | |
10�F51
���d���S����艺�ł́A���������Ȃ�A�����ď��������֍s���铹�ƂȂ�B
 | |
10�F53
�Ō�̕���_L�ɒ������B����������āA���̋��������R��12�ӏ����̕���_����A����_���x�Ȃ�ǂ��̎R�ɂ������Ă��Ȃ��B���i�����ɂ́u�����ǃ^���N�ց@�����̐�ʍs�o���܂���v�A���̓��ɂ́u�c���R�蒬�W��O�o�R���ցv�ƈē����������Ă���B
���̎R�ɂ���ē��́A�S�ē���l���ɂ��t����ꂽ���̂ŁA�����Ƀv���x�j�����d�˂����̂Ƀ}�W�b�N�����ŁA�J���[�j���ŗ����ɂ�������Ă���B��������Ă͂��Ȃ����f�p�Ȃ��̂ōD���͎��Ă邪�A�O����������悤�ɁA�����ɐj���ł�������Ă���_���C�ɂ���Ȃ��B
 | |
10�F57
�����̑����������ד�������ƁA�����ɕP�H�s�����ǔ����R�z���r�̉~�`�^���N���������B�����̂��ȂƂ����܂ŗ������A�[����o���Ă���Βi�Ƃ��ǂ��L�h�S���̕Ԃ����t�����t�F���X�ɎՂ��Ă���B�Βi���炢�J�����Ă��悳�����Ɏv���̂������d�Ɋu������Ă��Ă��āA�������牺��͕̂s�\���B
 | |
����ł����߂��ꂸ�ɁA�Βi�ۂ̃t�F���X�ɔj��ڂł��Ȃ����ƌ��ɍs���ƁA���ʎR�̎�O�̏��R���甒�����オ���Ă���̂��������B66.6m�O�p�_������䗧�O�R�̓����̕W��60m�قǂ̏��R�ŁA�A��ケ��ȎR�ɓo��l�͂��Ȃ����낤�ƒ��ׂĂ݂���A�P�H�M�R�T�����O�R�̓��̉��@�R�Œ��ӂ��ׂ��͐l�ԁI�Ƃ����L�^�����Ă��܂����B
�������Ă���̂����܌����邪�A�R�Ύ��͒��Ɍ������Ă���悤�őS�R�ۏĂ��ɂ͂Ȃ炸�ɂ��݂������B
 | |
�c���R�蒬�o�R����
11�F08
����_L�܂ň����Ԃ��A�c���R�蒬�o�R���������B�ʐ^����z���r�֍s�����̋����ƈÂ��������邪�A�z���r�̂Ȃ���������͂����Ɣ����̐�[�܂œ��������Ă����͂����B�z���r�̓����t�F���X�ۂ���荞��ōs������A���Ղ����тĂ���̂����邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B
 | |
11�F14
�c���R�蒬�o�R���ւ́A���Ζʂ��҂��Ă����B�����̐����}�Ζʂ�^�������ɉ���A�����������₯�ɍL������a��ȖX�����𗊂�ɁA�]�������Ȃ��悤�ɕK���ɉ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���̃p���_�C�X�߂Â�����A���₷�łɂȂ��Ă��܂������_�R�i�P�H�s���O��667.9m�j�Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ��g�����[�v���w偂̑�����ɂ���Ă���͂����B
 | |
11�F18
���Ζʂ�����I����ƁA�����R�ł͒������|��������тɂȂ��Ă���B
 | |
11�F20
�쑤���c���R�蒬�A�k�����c�����B���̋��E�ɂȂ��Ă��铹�H�ɉ���A�ʐ^�����̓d���ɂ́u�c�����꒚��24�v�ƕ\�����t�����Ă���B�ł��A�����͎R���ɂ������ē����Ă�ł���ʂ�ɓc���R�蒬�o�R���ɂ���B�ʐ^�̍��[��O�Ɍ����镽���̌������u�c���R�蒬�W��v�����A�\�D�������邱�Ƃ͏o���Ȃ������B
 | |
�n�C�J�[�͂��f��̇�3�c�����o�R��
11�F27
�z���r�֓o��K�i�̎�t�͂ǂ����ƎR����100m�قǖk�ɐi�ނƁA�t�F���X�ƗL�h�S���Ɓu�W�҈ȊO�����֎~�@�P�H�s�����ǁv�̌x���Ɏ��ꂽ�u�P�H�s�����ǔ����R�z���r�v�̕\�D�̂�����{�݂��������B
�t�F���X�����ŗL�h�S���̂Ȃ��N�����[�g�����������A��Ŗi���܂����Ă��錢�ɂ���ɑ�i�����ꂻ���Ȃ̂Œ��߂����A��������3�c�����o�R���i�P�H�s�����ǐE����p�j�Ƃ���B������҈�o�R�������邱�Ƃ��������Ă���̂ŁA����Ŕ����R�ɂ͏\���̓o�R�������邱�ƂɂȂ�B
 | |
�����R���痣��ĎR�Ύ������
11�F59
�悪�����Ă��܂��������������锪���R���痣��āA�R�Ύ�����ւƑ��������Ă݂��B
�ʐ^�E���̏������F���Ȃ��Ă���Ƃ��낪�R�����ՂŁA�K���Ȃ��Ƃɐv���ȏ��Ί����̂��ߔ�Жʐς͏��Ȃ��A�V���ɍڂ�悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ������B�܂������𑱂��Ă����������������A���S�����m�F���邽�߂̂悤���B
�ł��A�ō��C�������N���߂�30�x���������ӕ���o�Ă��邪�A���R���ȂǍl����ꂸ�A�o�Ό����͂Ȃ�Ȃ낤���B
 | |
�R���Ŋ������̂��̂��߂ɕ���������n�C�J�[��A��g��ň͘F���������炦�Ċy�����ɒc�R���邷��n�C�J�[�����邪�A�w�̗p�S�x�̑�����v���m�炳���o�����������B
�����R����܂Ŗ߂�
12�F15
���łɓ��@�ȂǖY�ꋎ���Ă��܂������A�����R�o�R�����S�T���̎g�����܂��ʂ�����Ă��Ȃ����Ƃ��v���o���A�c���R�蒬�o�R���܂Ŗ߂�B
12�F22
�ł��A���̖k�������ւ̋}�o���[�g�͕��ʂ���Ȃ��B�P�H�s�����ǒ����r�Ŗ{���̔��������Ւf���ꂽ���߂ɁA���R�����I�ɏo���Ă��܂����������B����������������₷���}�Ζʂ��A�ɂ��܂�Ȃ���o�艺�肷�邤���ɂ������������ɓ������L����A����̕���2m�ȏ�����邪�[���������Ȃ��ςȓ��ɂȂ��Ă���B
 | |
12�F37
�k�������̖��������A����_K��F�̊Ԃ́A�������������̎����͉�����肪�Ȃ�������B�������H�ɂȂ�Ƃ��ꂮ�炢�̕��́A�w偂̑��̑��A�ƂȂ�₷���̂ő�ςȓ��ɕς���Ă��܂��B
 | |
12�F44
�����R����ɖ߂蒋�H���Ƃ�B�����܂ł�3�l�̃n�C�J�[�Ƃ������U���҂ɏo������̂����A�����1���ԋ߂����Ă��N������Ă��Ȃ��B�݂�ȕP�H����ӂł���Ă�����A�P�H�َq���ɍs���Ă��܂����̂��ȁB
�����R�̍Ō�͐�������
13�F35
�����ǂ��ւ������ꓹ�̂Ȃ���{���̐��������c���������B���c�ɂ������A�����R�������Ɂu�c���R�蒬�ցi�҈䓌�R�����j�v�̈ē��������鐼�։��铹�֓���B
 | |
13�F39
����n�߂͌��ʂ����悭�u�����A���̃��[�g�͓W�]�����Ȃ̂��v�Ɗ������Ȃ����B�ł��A���̐�̔����̊ɂ₩������A����Ȃ��Ƃ͗L�蓾�Ȃ��̂͒n�`�}������Έ�ڗđR�Ȃ��Ƃ��B
 | |
13�F42
�����Ɋɂ₩�Ȕ����ɂȂ�B�^�������ɂ��t����ꂽ���낤�ɁA�X�ɉ��������̂��E�l�E�l�Ə������֍s���铹�������B
 | |
13�F47
������M�p�e���r�i���e�i�������Ă��邪�A�g���Ȃ��Ȃ��Ē����������o�����̂��낤�B���p�@��{�b�N�X�͒n�ɗ����A�ؐ��d�������������|�ꂻ�����B
 | |
13�F49
���[�ɖʔ������Ȋ₪����A�u�o���Ă݂�v�ƗU�킽�悤�ȋC�����ēV�ӂɗ����Ă݂��B���߂́A�u���[��A�Ⴂ���炱��Ȃ��v���炢�ŁA�ߓx�̊��҂͎����Ȃ��ق����悢�B
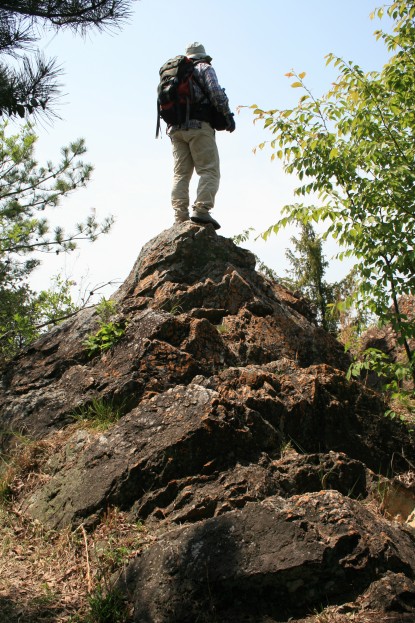 | |
10�F53
�����R�ɓ����J�����l�͋Ȃ��������Ƃ��匙���������̂��A���̐������̓����^�������ɂȂ��Ă��܂����B�ł��R���͐^�����������A�����Ȃ����Ă����ق������킢�[���Ǝv���̂́A���̐S�����P���Ȃ����Ă��邹�����낤�B
 | |
14�F05
�ɂ₩�����������������Ȃ�{�����������̂��A�ԓy�̃��[�v�ꂾ�B�����͊����Ă���̂Ń��[�v�Ȃ��ɕ��ʂɉ���邱�Ƃ��ł��邪�A����ł͎R�s�L�^�\����Ȃʔ����Ȃ��B����ɘA���ʐ^���B��ƁA���̏�ɐ����Ă��������ʂ���邱�Ƃ��ł���̂��ʔ����B
 | |
�A�����Ĕ��y�̃��[�v������������A������Ⴂ�R�Ƃ͂����V�т�������������Ă��܂��̂ŁA�����B�ǂ�����J�オ��ɂ̓c���c���Ɗ��肻�����B
14�F10
���d���S���u�a�����@��v�̉�����蔲����ƁA�����o�R���͂����������B�ɂȂ��Ă��������{�̑��d���S���́A�Ȃ����t�F���X�Ɍ��d�Ɉ͂܂�Ă��Ē��ɐG�ꍇ�����Ƃ��ł��Ȃ��B
 | |
14�F15
�S�����牺�́A���d�������H�ł���̃v���K�i���o�R���܂ő����Ă���B
 | |
14�F19
�܂����[�v������āA�ǂ��ɉ����̂��Ǝv���������o�R���������B�����Ȃ胍�[�v�ꂩ��n�܂锪���R�A����Ȃ����݂��B
 | |
�o�Ă����Ƃ���́A�����Ί_�ɋ��܂ꂽ�����R���痬��o���k��?�̘e�B�����ɂ͓o�R���̈ē��ȂǂȂ����A�E��Ί_�̏�ɂ́u�̗p�S�v�̏����H�W���W�����t�����Ă���B����ɂ������ē��ʂ�ɁA���̌������ɂ́u�҈䓌�R�����v���������B
 | |
�R����100���P�ӂ̉�̓Ďu�Ƃ��t�������낤�ē��ɏo����тɁA�u�j���Ŗɂ�����₪���āA�̒ɂ݂������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̒Ⴂ��n����Y���v�ƓłÂ��Ă����B���̂��тɁu���ꂪ����L���̊��ɂ₳�����A���R�ɂ͘I�قǂ����S�������Ȃ��ē����v�Ƃ������̂𗧂Ă悤���ȂƂ��v�������A���R�̒��ɐl�H�����������ނ̂́A���݂��̂Ă�̂Ɠ������Ƃ��Ǝv���������B
�����R�ɍ炢�Ă����ԁX
�ǂ��̎R�ɂ��炢�Ă���A�悭��������Ԃ����炢�Ă��Ȃ������B�R�o�m�~�c�o�c�c�W�͏I���A���}�c�c�W�͐��肪�߂��A���ꂩ��̓��`�c�c�W�̋G�߂��B
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
�X�|���T�[�h �����N
�b�R�s�L�^�ɂ��ǂ� �b�z�[���ɂ��ǂ� �b�{�y�[�W�̃g�b�v�b