烈風吹きすさぶ竹田城
スポンサード リンク
平成22年3月20日(金) メンバー おひとりさま
JR播但線竹田駅〜竹田城〜JR播但線竹田駅
播磨の山々の“しみけん”さんの山行記を参考に、その通りに竹田城を登ってきた。
竹田城は今から約400年前、関ケ原の戦いから43日後の西暦1600年12月3日、最後の城主であり石垣を築いた赤松広秀の死とともに廃城となった。だが山上に築かれた雄大な石垣は400年の年月を経ても崩れることなく、中世山城跡として日本でも屈指のものとしてその姿をとどめている。
一般的に山城は交通の要衝近くの山上にあるのがほとんどで、人里離れた山奥には存在しない。この竹田城もその例に漏れず、今は播但連絡道路とJR播但線、国道312号線にはさまれた標高353.7mの古城山(虎臥山)の山頂に位置している。自動車なら播但連絡道路・北近畿豊岡自動車道和田山ICから、山城跡近くまで登る車道を利用すれば、老若男女誰でも気軽に登城出来る単なる観光地に過ぎない。
それが竹田城東麓のJR播但線竹田駅から山道を登ると、短いながらも山登りの雰囲気を味わえ、登りきると忽然と現われる雄大な石垣、そして見下ろす景色は、車で登ったのとは一味も二味も違う。と、思う。
それでは姫路からJR播但線の旅を楽しもう
山陽本線姫路駅から山陰本線和田山駅へ至る播但線は、寺前駅以南のみが電化されているため、全線を直通運転する普通列車はない。寺前駅で電車から気動車に乗り換えなけらばならず、運転本数も南側と北側では大きな差があり、時刻表を見ずに適当に行くと寺前駅で1時間近く足止めされるので注意が必要だ。
電化区間の使用車両は大阪環状線のをもっと赤くしたような、何の変哲もない2両編成のものだ。だが、駅に着いても乗客が戸開ボタンを押さなくては扉は開かず、無人駅もあるワンマン運転なので整理券発行機とバスみたいな料金表示板、そして運転台の後には料金箱まであるが、さすがに降車ボタンまでは付いていない。でもトイレはある。103系なのに変われば変わるものだ。
7:39
姫路駅発寺前駅行きの電車が出発。車内は沿線に高校が数校あるため学生が多く、立っている人もいて、これが平日なら満員になるんだろうな。我が物顔で仲間内で声高に話し、携帯電話をかけるアホ学生までいて、ほとんど無法電車だ。電化区間の運転本数は多く、単線の播但線は行き違いの待ち時間が長めだ。
8:41
学生とほとんどの乗客は終点に着くまでに降りてしまい、寺前駅に着いた時には乗客は数人になっていた。
 | |
寺前駅で和田山行きに気動車の乗り継ぎまで15分。留置線には銀の馬車道のラッピングされた電車や気動車があり、あっという間に時間は過ぎてしまった。
 | |
 | |
8:41
電車は3編成がラッピングされているが、気動車でラッピングされているのは留置線の1両だけ。なので、姫路駅から乗ってきた電車が着いたホームの反対側にやってきた和田山駅行きは、普通のキハ41型の2両編成の気動車。色は播但線電車と同じ濃い朱色。
 | |
9:21
生野峠越えをして、横を流れる川も市川から日本海へ注ぐ円山川と変わり、播但線の終点和田山駅の一つ手前、竹田駅に着いた。姫路から1時間42分、運賃1,110円の旅だった。
竹田駅は有人駅(民間委託かな)で、竹田城に合せたような駅舎。改札北側は待合室、南側は「わだやま観光案内所」となっている。登る前に山城模型や綺麗に撮られた写真を見て事前に情報を仕入れるか、あるいは白紙の状態で登り感動をさらに大きなものとするかはあなた次第。ちなみに私は後者を選択した。
 | |
駅裏登山道の登山口は駅の裏
9:26
駅前広場ではタクシーが登城客を待ち、同じ列車から降りた男性二人連れはタクシーに乗って竹田城に向かったようで、城跡下まで10分ほどで着くようだ。
駅前広場の案内板を見ると、登山口は駅の真裏から始まっている。今いるのは駅の表で裏に行くには、案内図だと北に回ったほうが近いように読めるが、先達は南の「第三殿町踏切」へ回っていて、ここは率直に従うことにする。
 | |
線路近くの道を行くのが一番近いが、表通りまで出てみる。「歓迎 竹田観光協会」ゲートの先に左右に延びるメインストリートは、人も車の姿も見えず静まり返っている。下の写真、歓迎ゲートの右側はこの街の唯一のお土産物店「お土産処虎臥屋」で、駅の観光案内所でも幾ばくかの登城記念品を販売していた。
 | |
9:38
通りがかりの、法事に向うおばさんに話しかけられたりして、そして線路沿いを南に進み人だけが渡れる「第三殿町踏切」で虎臥城公園から寺町通りに出た。
竹田城は虎が臥せているようにも見えることから「虎臥城(とらふすじょう、こがじょう)」とも呼ばれ、それが東屋やベンチやトイレのある公園の名になり、善證寺・常光寺・勝賢寺・法樹寺と並んでお寺が建つ通りが寺町通りだ。
 | |
白壁を載せた石垣とタイル張りの道の間を流れる竹田川には、鯉たちが気持ちよさそうに泳いでいる。川面の石段を降りると、いつも餌を貰っているところなのか鯉たちが寄ってきて、頭を撫でても逃げようとしない。
 | |
9:45
列車を降りてから20分程かけて法樹寺北側の、「竹田城址登山口」と刻まれた石柱の立つ登山口に着いた。列車を降りたところから10mも離れていないのに、えらい遠回りの道だった。
 | |
登山口北側の忠魂碑公園(駐車可)には『“ひょうご豊かな森づくり構想”に基づく里山林整備事業 「日本一の山城」の森 案内図』があり、竹田駅からこの登山口までは約200m5分となっている。それが4倍の20分もかかっているのだから、竹田城跡まで約500m20分は私の足では1時間はかかるだろう。
 | |
「日本一の山城」の森 案内図
そびえ立つ石垣を目指して登っていく森。
この山の上には「国指定史跡“竹田城跡”」があり、自然石を用いた石垣が昔のたたずまいを思いおこさせます。その足元をとりまく森が里山林として整備されました。春にはヤマザクラとツツジの花が咲き、秋にはコナラの黄葉や低木類の赤い実が訪れる人の目を楽しませてくれます。
里山を登ってたどりついた竹田城跡からは、竹田の町の眺望はもとより、360度の大パノラマがまっています。
また、竹田駅の西側に立ち並ぶお寺と神社をめぐる道は「寺町通り」と呼ばれ風情のあふれる道です。山を下りた後のんびりと散策してはどうでしょう。
なお、竹田駅から竹田城跡に至る道は環境庁の「近畿自然歩道」に選定されています。−みんなでこの森を守りましょう−
- たきび、たばこの吸殻やゴミの投げ捨てはやめましょう。
- 樹木などを大切にしましょう。
- ゴミは必ず持ち帰りましょう。
【“ひょうご豊かな森づくり構想”に基づく里山林整備事業】
この区域は、地域の皆さん方のご協力のもと、景観や多用な動植物を保全し、保健や森林学習の場に活用するため、県内の林地を開発した方々の協力金により、森林の整備や歩道の開設などを行いました。
平成12年3月
兵庫県・和田山町・(社)兵庫県森と緑の公社
駅裏登山道で竹田城へ
9:48
駅裏登山道は、コンクリ舗装の激急な車道として始まり、一登りで墓地に突き当たり終わってしまう。
家々が立ち並ぶ古城山と円山川にはさまれた平地は、昔も人々が暮していたことだろうが、案内看板によると当時のお殿様・家臣団は少し高いこのあたりに居を構えていたという。
 | |
屋 敷 跡
このあたりは、今から400年ほど前(1600年頃)竹田城の城主や家臣団のお屋敷があったとされる場所です。彼らは、政務あるいは戦の時などにお城に登り、それ以外の時は麓のお屋敷で暮していたと考えられています。
これから皆さんが登る道は、昔の人も同じように竹田城に登っていった道と考えられます。竹田城の上からは、「なぜここにお城を造ったのか」を納得させられる景色を見ることができるでしょう。
墓地に入る手前に右へ山道が登っている。「竹田城跡登山口」と表示された、自立式の雲海に浮かぶ竹田城の写真付きの道標が立っている。この先、同じような道標や城跡までの距離を示すものが、目障りにならない間隔で設置されていて道迷いの心配は全くない。
 | |
9:52
「天主まで920m」の案内板のところに鹿柵扉がある。
「天主」とは「天守(閣)」を意味しているものと思うが、調べてみると天守は殿主、殿守、天主とかの字も当てられるとのこと。「キリスト教の神」がおわすところの意味の「天主」ではなく、隠れキリシタンの末裔の御業ではなさそう。
 | |
「竹田城跡」登山道です
こちらの扉を「押して」開けて通行してください。通った後は、必ず扉を閉めて」下さい。
和田山町観光協会
里山には付き物の鹿柵と扉だが、初めて見る人にとっては山の中にフェンスが続いていて、この中は私有地なのかなと勘違いするかもしれない。
9:53
今は植林されてしまっているが、明確な削平地と低い石垣があり、その間に石段の道が続く。昔はここに竹田城関係者の屋敷があったのか、それとも単なる畑地跡なのかは判断がつかないが、いずれにしろ昔はこの辺も人々の生活の場であったのは間違いない。それが今は手入れも行き届かない植林に成り果てている。
170年程の竹田城の歴史の中で、石垣を築いたのは最後の城主「赤松広秀」の治めた15年ほどの時代で、近郷近在の農民は城造りに駆り出され田は荒廃し松が生えたというが、今は杉がその役目を担っている。
よく知られているように赤松氏は播磨を長く支配した一族で、よその国の農民を人とも思わず牛馬の如くこき使ったのに違いない。地元の人は、そんな思い出すのも嫌な歴史のある竹田城をどのように思っているのだろう。
 | |
まだ春浅く、草木の芽生えも感じられないが、スミレだけが可憐な花を咲かせ目を楽しませてくれる。
カタクリやユキワリソウを代表とする派手目の早春の花々を溺愛するのが今様のトレンドのように感じるが、私はどこにでも咲いているスミレが大好きだ。
 | |
9:57
石段の道が丸太階段に変わると、しみけん氏の山行記録にあった砂防ダムが現われた。ともに平成18年1月に竣工した、左は「古城下川(その1)堰堤」、右側は「古城下川(その2)堰堤」だ。
堰堤直下に立つ砂防指定地標柱は「上古城川」となっているが、砂防堰堤表示は「古城下川」となっていて、些細なことだが「小さなことからこつこつと」を人生訓とする私にとっては大きな疑問が残ってしまった。
 | |
中央部をパイプ構造にすることで、普段は土砂を通すことで上流部に堆積させず、洪水時は土砂を一時的に受け止めるが、洪水後には徐々に土砂を流失させることにより、より自然に近い環境を保つという、透過型砂防堰堤だ。平成16年10月20日の台風23号の災害復旧工事によるものだ。
 | |
10:06
砂防堰堤工事用道路の開削により、本来の登城道は失われ、木板で土留した階段道だ。出来ることなら石段の道を復活して欲しいものだが、この赤土の斜面に石段を組んでも流されるだけだろう。
 | |
10:09
砂防ダムを過ぎると、また石段の道に戻った。「天主まで750m」とあり、あまり距離が縮んでいないのが恨めしい。
 | |
早春の葉を落とした林越しに竹田の町並みが見えるが、麓からあれだけ見えていた石垣は全行程を通して全く見えない。
石段に使われている石は積み木のようなものが多く、今風の石段によく使われている輸入石材の三角形のものではない。このことからは400年前のままの石段だと即断は出来ないが、かなり古いものであるのは間違いない。
 | |
10:18
虫かごみたいな休憩舎が道端に立っている。中に入っても虫かごみたいで、風雨を防ぐためなら周囲を板壁にすればよいのに、展望を楽しむならもっと低い手摺だけでよいのに、なんかちぐはぐな造りだ。
風は穏やかで、暑くなってきたのでここでジャケットを脱ぐことにする。
 | |
10:28
舗装車道の終点に着いた。竹田城の西側にある中腹駐車場(50台、トイレあり)から城跡を半周する車道の終点で、Uターンはできるが駐車スペースは用意されていない。今日は1台の車しか止まってないが、繁忙期にここまで車を入れると大変なことになりそうだ。
「史跡 竹田城址 兵庫縣」と刻まれた古い石柱と案内解説板が立っていて、コンクリ舗装の歩道を登れば竹田城はもうすぐだ。
 | |
史跡 竹田城跡
−遺構について−
竹田城は別名「虎臥(とらふす)城」という。嘉吉年間、山名持豊(宗全)が播磨・丹波から但馬への侵入路に位置する要衝の地に13か年を費やして築いたものと伝えられてきた。築城当時の城には石垣はなく、曲輪を連ねただけのものであった。それが現存の完成された城郭に整備されたのは、天正〜慶長初期と推定されている。
石垣は近江穴太(あのう)衆の手による穴太流石積み技法を用いた“野面(のづら)積み”である。石材は現地のほか山麓周辺から集めたものであろう。
遺構は最高所の天守台をほぼ中央に置き、本丸以下南方に南二の丸、南千畳、北方に二の丸、三の丸、北千畳を築いている。さらに、天守台の北西部には花屋敷と称する一郭があり、主郭のなかでも最も低い位置にあるため、南北には向かい合った塁状石垣列を築いている。
規模は南北約400m、東西約100mで今なお当時の威容を誇っており、山城として全国でも数少ない現存する遺構である。−城主について−
城は築城後、山名の家臣太田垣光景が初代城主となったと伝えられ以後太田垣氏は7代にわたりこれを守り継いだ。応仁の乱では2代城主景近が京都へ出陣した祭、夜久野へ来襲した細川軍を景近の二男宗近が打ち破ったという。
永禄12年(1569)羽柴秀吉は但馬へ攻め入り竹田城を攻略した。天正5年(1577)再び秀吉軍の攻撃をうけ竹田城はついに落城した。このあと秀吉は弟子一郎を城主として城内の整備を命じている。同8年(1580)桑山重晴が城主となり、13年には四国征伐等で戦功のあった赤松広秀を竹田城主として入れた。広秀は、九州征伐、朝鮮の役等に出役したほか、文化人としても儒学者藤原惺窩との親交も厚く、領民には産業を奨めて深く敬慕された。
関ケ原の役には西軍に属した。関ケ原敗北後、徳川方として鳥取城を攻め、戦功をあげたにもかかわらず、城下に火を放ったことで徳川家康の忌避にふれ、鳥取真教寺において自刃し果てた。享年39歳、慶長5年10月28日のことである。国史跡 (昭和18年9月8日指定)
所在地 兵庫県朝来郡和田山町竹田字古城山169番地和田山町教育委員会
竹田城登城
10:33
竹田駅で列車から降りてから1時間12分、ようやく竹田城の石垣が間近に迫ってきた。予想していたよりも石垣の規模は大きい。
竹田城より後に築城された作用平福の山城利神城(1631年廃城)の荒れ果てた姿を見ているので、よくぞ400年の年月を経ても築城時と変わらぬ姿を私の前に現わしたかと思うと感動してしまった。でも400年は私の年齢の約8倍にしか過ぎず、それほど長い年月ではないのかもしれない。
 | |
駅裏登山道が辿りついたところは大手口だ。大手口と言えば城の表玄関、ここから入城するのが山城愛好家としての正しい行いだ。
 | |
ここからは、解説は写真に付けたキャプションのみとして竹田城の雄大な姿をじっくりと味わってもらおう。なお「人の写っていないのは写真じゃない」主義を掲げる我が播州野歩記なので、ちょっと目障りな人物が常に登場するが、それは致し方ないことと我慢して欲しい。
この写真を撮るころから急に強風が吹きはじめ、時には身を屈めたくなる烈風も。普通の三脚ならカメラごと倒れてしまうがSLIK 三脚 スプリントPRO2 ガンメタリック SL-1080GJ(アマゾンのページにジャンプします)なら、三段階調節の脚をほぼ水平まで広げることができ、どんな烈風の元でも倒れることはない。重さはわずか940gと山行きにも最適で、私のお気に入りだ。
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
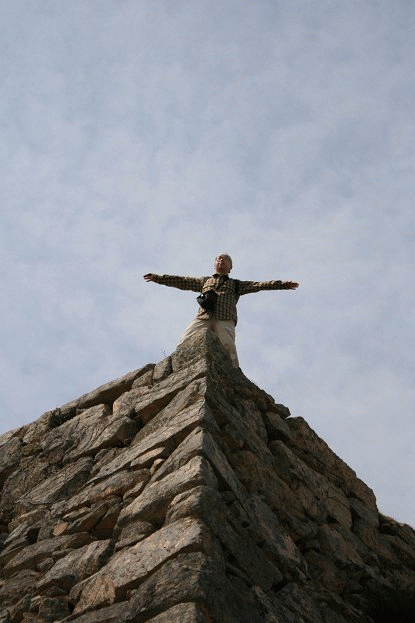 | |
 | |
 | |
>
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
さてこれ以上南へは行けないし、引き返そうか。
 | |
 | |
 | |
12:50
そろそろ帰ろうかと時計を見ると、ガーンあと10分で列車が出てしまう。そして次の列車は1時間40分後だ。もう一回りするか。
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
下山
13:21
下山開始。下山ルートは登路と同じ駅裏登山道にしたが、時間は十分にあったので隣のピークを通る「観音山登山道(0.9km約40分)」にすればよかったなと、帰宅後反省。
13:41
20分足らずで法樹寺北側の登山口に下山完了。ちょうどやって来た和田山駅行きのラッピング列車を撮影したり、竹田駅の観光案内所で事後学習にいそしんだりして帰りの列車を待つ。
 | |
14時31分の寺前駅行き列車は、寺前駅で2分の待ち合わせで姫路駅行きに接続し、15時59分に姫路駅に到着した。
スポンサード リンク